養殖産業は、乱獲、気候変動、水産物消費量の増加による世界的な需要に牽引されている。養殖産業は、乱獲や気候変動、水産物消費量の増加といった世界的な需要に後押しされている。乱獲と環境悪化により、日本の天然魚資源は基本的に枯渇している。経済成長と食料安全保障の両方を促進するため、日本政府は沿岸での養殖を刺激する規制を設けている。日本の水産物生産全体のかなりの部分が養殖によるものである。最も一般的な魚種は、カキ、タイ、ブリである。
この報告書はこちらから請求できる: https://www.sdki.jp/sample-request-104975
当社の水産養殖市場分析調査レポートによると、以下の市場傾向と要因が市場成長に貢献すると予測されています:
シーフードの消費量の増加―個人の健康意識がますます高まるにつれ、シーフードの栄養価、主にタンパク質の含有量が高く、心臓や脳の健康に非常に役立つオメガ3脂肪酸の豊富さについての認識が高まっています。
技術のさらなる進歩―水産養殖の進歩、特に繁殖、病気の管理、飼料効率の点で、業界の生産性と持続可能性が大幅に向上しました。選択的育種プログラムにより、損失を最小限に抑えながら収量を倍増させ、成長が早く病気に強い魚種が誕生しました。また、高度な疾病管理は、ワクチンとバイオセキュリティプロトコル、つまり発生を防ぐための予防措置に依存しています。追加の飼料技術により、より効率的でおいしい飼料も開発されており、無駄が最小限に抑えられており、魚の成長が速くなりました。
水産養殖市場における水産養殖の輸出という観点から、日本の地元企業はどのような恩恵を受けますか?
国の豊かな食の歴史と高品質のシーフードに対する世界的なニーズを考慮すると、日本には輸出用の水産養殖の地元企業にとって計り知れない機会があります。
さらに、地元企業も水産養殖製品の輸出能力の向上に成功しています。産業界、学術機関、政府部門間の連携により、洗練された育種方法と飼料の最適化が促進されており、製品の品質と収量が向上しました。Maruha NichiroとNippon Suisan Kaishaなどは、国際的な需要に応えるために、持続可能な水産養殖の実践と国際市場への参入に投資しています。
水産養殖市場は、環境に基づいて、海洋水、淡水、汽水に分割されています。淡水セグメントは、予測期間中に市場を支配すると予測されています。世界的に魚の需要が高まる中、水産養殖は大幅に成長しており、特にティラピア、コイ、ナマズなどの淡水種が主な食餌となっている地域では、この成長を促進しています。
市場課題
持続可能な水産養殖は常に水質汚染、生息地の破壊、野生魚個体群への病気の蔓延の影響を及ぼしますが、管理が不十分な養殖場は周囲の生態系に悪影響を及ぼし、規制上の課題を引き起こす可能性があります。
原資料: SDKI Inc 公式サイト
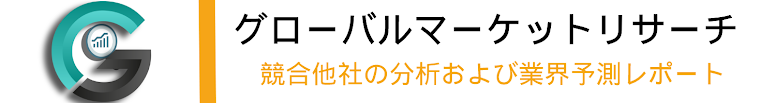

コメント
コメントを投稿